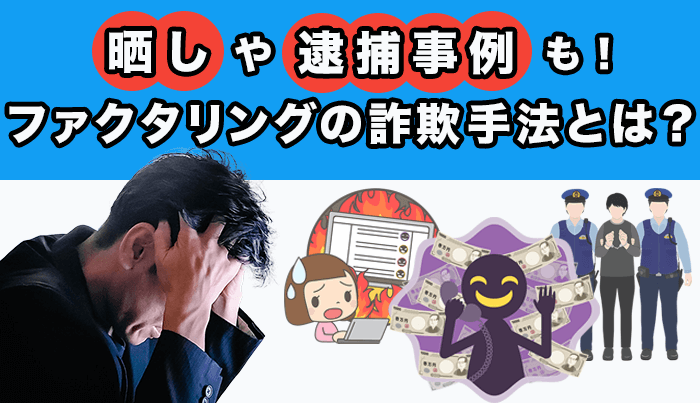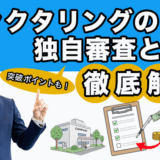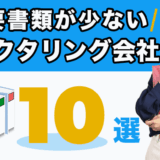PR
『ファクタリングを利用してみたいけど詐欺が心配』『ファクタリングの詐欺手法や、晒しに合った事例、逮捕事例はある?』
ファクタリングは、当事者同士の合意によって成立する民法上の契約であるため、銀行融資のように特別法で手厚く保護されているわけではありません。そのため、契約内容によっては十分な保護を受けられず、悪質な業者によるトラブルや詐欺に巻き込まれる可能性もあります。
この記事では、ファクタリングの詐欺手法について、ファクタリング会社、利用者それぞれの事例紹介から、詐欺にあわないための対策、詐欺にあってしまった場合の対応も解説します。
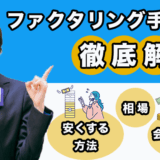 手数料が安いファクタリング会社!手数料を安くする方法と相場も解説
手数料が安いファクタリング会社!手数料を安くする方法と相場も解説 ファクタリングの詐欺事例|事業者、利用者それぞれの詐欺を解説

ファクタリング詐欺は事業者(ファクタリング会社)、利用者(事業主)それぞれが行ってしまうことがあります。「うっかりしていた」「つい書類に手を加えてしまった」ということが重大犯罪行為に認定されてしまうかもしれません。
絶対にファクタリング詐欺はしない、ということを肝に銘じていただくためにも、事業者、利用者それぞれどのようなことがファクタリング詐欺に該当するのか紹介していきます。
事業者(ファクタリング会社)の詐欺(事例あり)
まずファクタリング会社が行うファクタリング詐欺について解説します。このようなことをファクタリング会社がした場合、詐欺罪として告発も可能ですし、民事上で損害賠償請求などもできます。
融資なのにファクタリングと偽った
実体は融資なのにファクタリングと偽り法外な金利を請求した詐欺です。融資の場合、金利は利息制限法によって規制されています。しかし、ファクタリングならば利息制限法の上限を超えても合法です。
もちろん、公序良俗に反するような高金利は民法上もNGですが、そのグレーゾーンを狙ってファクタリング詐欺を行います。
例えば、警視庁に逮捕された事例では、2016年11月ごろ~20年4月ごろ、貸金業の登録がない「ファクタリング会社」が香川県や宮城県の中小企業の経営者ら5人に計約1億3千万円を貸し付け、法定金利の8倍から34倍にあたる利息計約3千万円を受け取った疑いがある事件が報道されました。
「ファクタリング会社」社員は逮捕され、新聞で報道され、ネット上に晒されることとなりました。
中小企業狙い「ヤミ金」容疑 ファクタリング業者を逮捕|朝日新聞 2021年2月5日
法定金利上限(15%~20%)で15%だと仮定すると15%×8倍=120%
ファクタリング手数料を年利換算して100%を超えるのは珍しくありません。しかし、売掛債権の売却なら合法ですが、融資なら違法であり、ファクタリングを偽るのは立派な詐欺です。
契約時と違う極端に高額な手数料を請求した
契約時は手数料10%と言って契約書を取り交わしたのに、実際にファクタリングしたら25%だったというケースです。「契約違反だ」と言っても「ここに例外が(小さく)あり得ると書いてある。今回は例外的な事態だ」と言われてしまいます。
例外は突発的な何かが起きたときにはまだ考えられますが、今回はそういうこともなくスムーズに進んだはずです。それでも高額な手数料を理由なく請求されてしまうのは、ファクタリング詐欺と言わざるを得ません。
債権譲渡通知がないと言っていたのにあった
ファクタリング契約時に「債権譲渡通知は送らない」と説明を受けていたにもかかわらず、後になって取引先へ通知が送られていたというトラブルが発生することがあります。3社間ファクタリングならば債権譲渡通知を承諾していますが、2社間ファクタリングなのに債権譲渡通知が送られてしまう場合です。
債権譲渡通知は、売掛先に対して「債権が譲渡された」ことを知らせる重要な手続きであり、ファクタリングがバレます。結果、取引先との信頼関係にも影響を及ぼす可能性があります。2社間ファクタリングで債権譲渡通知する意味はあまりなく、契約にないならばファクタリング詐欺です。
ノンリコース契約のはずが償還請求権付きファクタリング(リコースファクタリング)だった
ファクタリング契約を「ノンリコース(償還請求権なし)」と説明されていたのに、実際には償還請求権付きのリコースファクタリングだったというトラブルが発生することがあります。
ノンリコース契約では、売掛先が倒産しても利用者が代金を支払う必要はありませんが、リコース契約では売掛金が回収できない場合、利用者に返済義務が発生します。売掛金の回収不能リスクもファクタリング会社に移転することがメリットなのに、そのメリットを打ち消すことであり、これを告げていなければファクタリング詐欺です。
なお、「償還請求権付きファクタリングは融資である」という判決(※)が出ていることも付記します。つまり、融資なのにファクタリングと偽った二重の意味での詐欺なのです。
「給与ファクタリング」できると言って個人客を集めた
いわゆる「給与ファクタリング」(給料ファクタリング)は、社会問題化しましたが、最高裁判決(※)によって「給料を担保とする融資である」という判決が出ています。つまり、給与ファクタリングではなく「給与担保融資」であり、融資である以上「金融業、貸金業許可を得た事業者」が「利息制限法範囲内の金利」で「信用情報照会」して行うものです。
許可されていない事業者が行うのは違法であり、それをファクタリングと偽るのはウソをつくことで当然詐欺です。今、給与ファクタリングを行う業者はほとんどないはずですが、まず詐欺の可能性を疑ってください。
利用者(事業主)の詐欺
ファクタリング利用者(事業主)もファクタリング詐欺をはたらくことがあります。売却できる売掛債権がない、金額が希望額に満たないなどファクタリングによって資金調達が難しい場合、詐欺行為によって「偽りの売掛債権」を作り出してしまうのです。
架空債権を売却した
実際に新聞記事になっているので、それを参考にしましょう。詐欺事業者は、自社が売り掛け債権を持っていると装い、ファクタリング会社に売掛債権買取を申し込んで約3億4600万円で買い取らせた事件がありました。
架空債権なのになぜファクタリング会社が信じてしまったのか、それは売掛先が大手企業であると謀るため、大手企業との取引を装い、問い合わせ用のメールアドレスを事前に用意していました。
「大手企業」との取引が実在するように信じ込ませるため、大手企業の社員のふりをしてファクタリング会社とやり取りしていたというものです。つまり、3社間ファクタリングでかつ、売掛先を自作自演していたというものです。
架空債権で3億円詐取容疑 イベント企画会社代表逮捕|朝日新聞 2020年12月4日
架空の請求書はプロであるファクタリング会社が見抜くだろうと思っていても、詐欺師の手口に遭うと騙されてしまう一例です。犯人の名前が新聞に出て、全世界に晒され、デジタルタトゥーとして残ってしまうことになります。
不良債権を売却した
ファクタリング詐欺の手口の一つに、実際には回収が見込めない、もはや焦げ付いている不良債権化した売掛債権を故意に売却するケースがあります。
利用者者が売掛金として提示する債権が、すでに取引先の経営悪化や倒産により回収不能であるにもかかわらず、事実を隠してファクタリング会社に譲渡する手法です。ファクタリング審査で「通帳コピー」が必要なのは、不良債権化して、振込期日に間に合わないような売掛先を排除する意味がありますが、何らかの理由によってそれが見落とされ、チェックされなかった多ため不良債権をファクタリング会社が買い取ってしみました。
明かな不良債権を有効な債権と偽るのは、立派な詐欺です。
請求書を偽造、捏造した
ファクタリング詐欺の中でも多い手口のひとつが、請求書を偽造または捏造するケースです。実際には存在しない取引をでっち上げ、架空の請求書を作成してファクタリング会社に提出し、売掛金の早期現金化を装う手法です。あるいは実際には100万円の売掛金だったのに、請求書を変造して「200万円」に変えて、本来よりも高額の資金を調達する方法です。」
詐欺罪だけではなく、「私文書偽造罪」も加わり、より悪質な犯罪になります。自治体や公共団体、官公庁などの仕事の場合、公的文書を偽造するので「公文書偽造罪」が加重される可能性もあり、後者のほうがより重罪です。
実際には売掛金が存在しない(あるいは金額が足りない)ため回収不能となり、ファクタリング会社が大きな損失を被る可能士絵も否定できません。
売掛債権(請求書)を二重譲渡した
同じ売掛債権(請求書)を複数のファクタリング会社へ二重譲渡するケースも詐欺です。ファクタリングは「A社からB日にC万円を受け取る権利」を売却するものです。
「A社からB日にC万円を受け取る権利」は1つしかないわけで、分割できません。1つしかないものを2社以上に譲渡できず、これを行えば2社目以上はないものを買わされたことになります。
ないものを買わされた「豊田商事事件」の最後がどうなったのかからもわかるように、詐欺師の典型的な手法になります。当然重大な詐欺犯罪だと言わざるを得ません。
売掛先からの入金予定が一つしかないにもかかわらず、異なる会社に対して同じ請求書を提示し、重複して資金を得ようとする詐欺を封じるため、ファクタリング会社は3社間ファクタリングや債権譲渡登記で自己防衛するしかありません。
ファクタリング資金を横領し返済しなかった
売掛債権を譲渡して得た資金を当初申し込み時に示していた目的以外に流用し、返済を行わないケースがあります。通常、売掛先からの入金はファクタリング会社へ支払う義務がありますが、事業者が資金を私的流用したり他の債務返済に充てた結果、ファクタリング会社への返済が滞る事態が発生します。
これを防ぐための3社間ファクタリングですが、利用者がかたくなに2社間ファクタリングを主張すると起きえる事態です。2社間ファクタリングの手数料が高いのは、このリスクがあるからです。
私的流用によって返済できなくなり、ファクタリング会社は回収不能リスクを負うことになります。当然、詐欺や横領として刑事責任を問われる可能性があります。
ファクタリグで詐欺に遭った時の対応を紹介
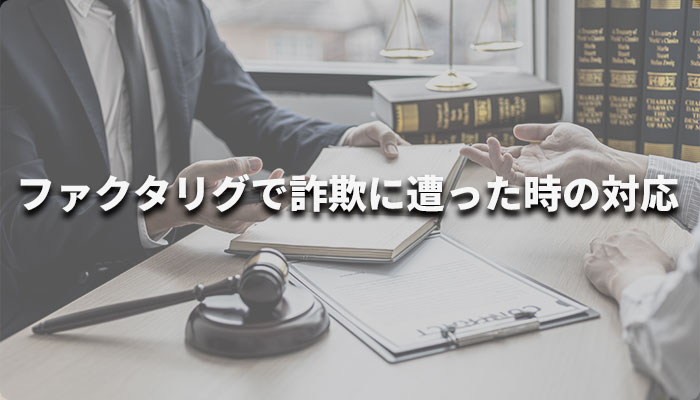
事業者も利用者もこのように「ファクタリング詐欺」に遭う可能性があります。明らかに重大な犯罪なので、しかるべき法的措置を取ることをおすすめします。
ファクタリング詐欺に遭ったときに具体的にどのような対応をすべきなのか以下で紹介します。
弁護士への速やかな相談
ファクタリングで詐欺被害に遭った場合は、速やかに弁護士へ相談することが重要です。請求書偽造や二重譲渡などのトラブルは、個人での対応が難しく、専門的な法的知識が必要となります。
弁護士に相談することで、契約内容の精査や債権回収の可能性を判断してもらえるほか、刑事告訴や損害賠償請求など適切な対応を迅速に進めることができます。被害拡大を防ぐため、早期の対応が大切です。
取引先や金融機関への連絡
詐欺被害に遭った際は、早急に取引先や金融機関へ連絡することが重要です。請求書偽造や二重譲渡などの不正が疑われる場合、取引先に事実確認を行うことで売掛債権の実在性を確かめられ、回収の可否を判断できます。
また、金融機関に状況を共有することで、口座の凍結や不正送金の防止など迅速な対応が可能になります。被害拡大を防ぐためにも、関係先への早期連絡は欠かせません。
証拠保全と事実関係をまとめる
証拠を確実に保全し、事実関係を整理することが重要です。契約書、請求書、メール、チャット(スクショ)、振込明細、通話記録など、ファクタリング詐欺トラブルに関連する資料はすべて保存してください。
時系列で状況をまとめることで、弁護士や警察へ相談する際に正確な情報を伝えられ、迅速な対応が可能になります。証拠の確保は被害回復の第一歩であり、後々の法的手続きでも極めて重要な役割を果たします。
捜査への誠実な協力
弁護士や警察による捜査、証拠集めへの誠実で積極的な協力が不可欠です。被害状況を正確に伝えるため、契約書や請求書、振込明細などの証拠資料を速やかに提出し、事実関係を明確に説明することが求められます。
虚偽の申告や情報の隠蔽は、捜査を遅らせるだけでなく、事件解決を遅らせます。捜査機関に適切な情報を提供することで、加害者特定や損害賠償請求につながる可能性が高まります。
ファクタリングで詐欺に合わないように知らないファクタリング会社は避ける
そもそもファクタリング会社を選ぶ際に、評価の低い業者や知らないファクタリング会社の利用を避けることが大切です。過去の実績や口コミ、登録情報を確認し、所在地や連絡先が不明確な業者とは契約しないよう注意が必要です。
特に、極端に低い手数料や「審査不要」「必ず資金化できる」など過剰な勧誘を行う会社は危険です。事前に複数のファクタリング社を比較検討し、信頼できる業者を選ぶことで、詐欺被害を未然に防ぐことができます。
ファクタリングで詐欺に遭わないためには
ファクタリング詐欺は重大犯罪ですが、その被害に遭わないことが第一です。そのためにはどのようなことに注意すべきなのか、簡単にまとめました。利用者が詐欺ファクタリング会社の被害に遭わないこと、事業者(ファクタリング会社)が詐欺利用者に騙されないこと、両方を含みます。
【利用者としての注意】信頼できるファクタリング会社を見極める
ファクタリングを利用する際は、信頼できる会社を見極めることが重要です。まず、ホームページがああるか、会社情報が明確に公開されているかを確認しましょう。手数料が不自然に安すぎる場合や「審査不要」「即日必ず100%現金化」など過剰な宣伝をする業者は注意が必要です。
利用者の口コミや実績も参考になります。口コミサイトなどで複数社を比較し、契約内容を十分に理解したうえで契約することで、トラブルを防ぎ安全に資金調達が可能になります。
会社の所在地、連絡先、実績、口コミ、登録情報などを事前に確認し、実態の不明な業者との契約は避けることが重要です。
【利用者としての注意】契約内容と手数料を必ずチェックする
ファクタリングを利用する際は、契約内容と手数料を必ず確認することが大切です。手数料の設定は会社によって大きく異なるため、事前に複数社を比較して相場を把握しておきましょう。
ファクタリング手数料の相場は以下になります。これより高いファクタリング手数料の会社は避けた方が賢明です。
| 2社間ファクタリングの手数料相場 | 10%~20% |
| 3社間ファクタリングの手数料相場 | 1桁%(5%未満ならなお良い) |
また、手数料以外に事務手数料や違約金などの追加費用が発生するケースもあります。ファクタリング業界は競争によって、かつてあった「事務手数料」「着手金」などの項目は手数料に一本化されています。それでもこれらの手数料以外の費用を請求するファクタリング会社は要注意です。
また、契約書には支払条件や償還請求権の有無など重要な項目が記載されているため、内容を理解せずに署名するとトラブルの原因となります。納得できる条件で契約することが安全です。「償還請求権あり」のファクタリングは「ファクタリングではなく融資」なので、要注意です。償還請求権付きファクタリングを求めるファクタリング会社は避けてください。
極端に低い手数料や「審査不要」「必ず資金化できる」といった甘い誘いには注意し、契約書の条項を十分に確認してからサインすることが大切です。
【事業者としての注意】取引先や債権の実在性を確認する
請求書の偽造や二重譲渡によるトラブルを避けるため、事業者(ファクタリング会社)は利用者の取引先の支払い状況や売掛債権の実在性を事前に調べ、リスクを最小限に抑えましょう。
事業者(ファクタリング会社)は取引先や売掛債権が本当に実在するのかを必ず確認することが重要です。実在しない取引先や架空の売掛金を使った契約は、当然利用者のファクタリング詐欺です。
請求書・契約書・入金履歴(通帳コピー)など、売掛金の発生を証明できる資料を利用者に事前に用意してもらい、内容が正確か審査でチェックしましょう。また、取引先の信用状況をファクタリング会社のネットワークなどを用いて調べることで、回収不能リスクを回避できます。
ファクタリングは融資ではないので、融資の信用情報照会は使えません。
詐欺は重大犯罪で甘く見ていると取り返しがつかなくなる
詐欺はちょっと人をだましたくらい、という印象を持っている方もいるかもしれません。しかし、ファクタリング詐欺で課される詐欺罪や横領罪はとんでもない重大犯罪です。軽い気持ちでファクタリング詐欺をしてしまうと、人生取り返しがつかなくなります。
詐欺罪・横領罪は逮捕され懲役刑もあり得る重大な刑法犯罪
以下を見てください。
| 詐欺罪 | 10年以下の懲役(罰金刑なし) |
| 横領罪 | 単純横領罪:5年以下の懲役、業務上横領罪:10年以下の懲役 |
これらの罪には罰金刑がなく、執行猶予が付かない限り懲役刑となります。1回のファクタリング詐欺で即時刑務所行きもあり得ます。そのため、安易な気持ちでファクタリング詐欺を行うと、取り返しのつかない事態になりかねません。
ちなみに請求書偽造など、書類関連の詐欺だとさらに以下が加重される可能性があります。
| 偽造の内容 | 問われる犯罪と量刑 |
|---|---|
| 請求書偽造 | 詐欺罪:10年以下の懲役 |
| 銀行通帳の偽造 | 私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役 私文書変造罪:3か月以上5年以下の懲役 私文書行使罪:3か月以上5年未満の以下 の懲役 詐欺罪:10年以下の懲役 |
| 契約書の偽造 | 私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役 私文書変造罪:3か月以上5年以下の懲役 公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役 公文書変造罪:1年以上10年以下の懲役 詐欺罪:10年以下の懲役 |
| 身分証明書の偽造 | 公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役 公文書変造罪:1年以上10年以下の懲役 偽造公文書行使罪:1年以上10年以下の懲役 詐欺罪:10年以下の懲役 |
| 確定申告書、決算書の偽造 | 私文書偽造罪:3か月以上5年以下の懲役 偽造私文書行使罪:3か月以上5年以下の懲役 詐欺罪:10年以下の懲役 所得税法、法人税法、消費税法違反:10年以下の懲役、若しくは100円以下の罰金、又はこれらの併科+追徴課税 |
| 商業登記簿謄本の偽造 | 公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役 偽造公文書行使罪:1年以上10年以下の懲役 詐欺罪:10年以下の懲役 公正証書原本不実記載罪:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
請求書は利用者が作成するものなので、偽造しても詐欺罪だけですが、上記は相手がある書類や公文書なので、さらに罪が上乗せされます。安易に考えていると本当に大変なことになってしまいます。「偽造」は「ないものを勝手に作ること、「変造」は「ある書類の数字を変えること(売掛金を勝手に増やす、支払日を勝手に変更するなど)」と区別します。
ファクタリング詐欺の結果社会的制裁として晒しや逮捕される可能性もあり
ファクタリングを悪用したさまざまなファクタリング詐欺は、重大なリスクを伴います。架空の売掛金を使ったり、虚偽の書類を提出して資金をだまし取った場合、詐欺罪に該当する可能性が高く、最悪の場合は逮捕され懲役刑も考えられます。
また、違法業者や正義の被害者、ネットのおもちゃにされ名前や会社情報をインターネット上で「晒し」されるケースも多く、社会的信用を大きく失う危険があります。ネットの晒しを受ければ、事実がどうなろうと(裁判で詐欺とならなくても)、デジタルタトゥーとして残ってしまいます。
さらに、金融機関や取引先との関係悪化、今後の資金調達の困難化など、事業継続にも深刻な影響を及ぼします。実際に詐欺など犯罪となれば、信用情報にも掲載されてしまいます。
ファクタリングを利用する際は、正しく、適正な契約を結ぶことが自己防衛にもつながります。
詐欺罪はファクタリング会社、利用者それぞれで起こる
ファクタリングにおける詐欺罪は、ファクタリング会社側・利用者側の双方で発生する可能性があります。会社側では、融資なのにファクタリングだと装う、過大な手数料をだまし取る、契約内容を偽る(償還請求権の有無)などの手口が問題となります。
一方、利用者側では、架空の請求書を提出したり、二重譲渡を隠して契約することがあります。これらはいずれも立派なファクタリング詐欺であり、詐欺罪や文書偽造・変造罪などに問われる可能性があります。
どちらの場合も刑事罰の対象となり、逮捕や実刑(刑務所)に至ることがあります。さらに、違法行為が発覚すれば実刑とならなくても、インターネット上での晒しや取引先からの信用失墜にもつながるため、絶対にやめましょう。
まとめ
ファクタリング詐欺は、事業者・利用者のどちらにとっても重大なリスクを伴う犯罪です。架空の売掛債権を売却したり、虚偽の書類を提出したり、虚偽の内容で契約を求めるなど不正な契約を行えば、詐欺罪として逮捕・起訴され、最悪の場合は実刑となり服役する可能性もあります。
また、実刑を受けなくてもインターネット上で会社名や個人名が晒されるなど、社会的信用を失う危険も大きいです。資金繰りに困っていても、安易に不正に手を染めることは避けてください。ファクタリングは正しい手続きで安全に利用することが重要であり、事業者・依頼人双方が十分に注意を払う必要があります。
ファクタリングには特別法がなく、民法の債権譲渡規定が適用されます。それだけ当事者の信用を重視しています。柔軟な取引を維持できるように、誠実な取引を続けていきましょう。